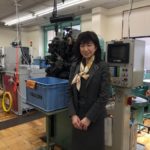- 2025-4-1
- 取材・インタビュー
危機が生んだ自社製品開発への歩み
東京都江戸川区の株式会社西川精機製作所は、精密加工業としてメッキ製造の治具等の製造を主事業とする一方で、多様な分野のユニークな自社製品の開発に取り組んできました。現在では、自社製品の売上割合は10%近くとなり、今後の事業拡大に向けて自社製品が事業の重要な位置を占めています。一回目の今回は、株式会社西川精機製作所の沿革と、これまでの自社製品への取り組みについてお話を伺いました。

株式会社西川精機製作所 代表取締役 西川喜久氏
創業の原点と歴史
御社の事業の歩みについて教えてください。
西川氏:1960年創業で60年以上の歴史があります。父の時代には、初めは1個何円という小さな部品を毎日何百個単位で製造する下請け企業でした。その後、メッキ工場の仕事や、ガスなどから顔を守る防塵対策面の部品製造などを手がけるようになりました。個々の部品をアッセンブリーしてより大きな部品を作るようになり、次第に何千円、何万円規模の製品を手がけるようになりました。
父が病気で倒れたことがきっかけで、私は大学卒業後すぐに入社しました。父が亡くなる1999年頃には、メッキ用治具においても最終形態まで組み上げる仕事にチャレンジするようになっていました。「部品屋」から「製品屋」への転換期ですね。その後、リーマン・ショック前までは、年商も父の時代の約3倍にまで成長し、2カ月に一度は納品先で1週間ほどの据付作業をするほどの仕事量がありました。
リーマン・ショックの危機意識がもたらした変革
リーマン・ショック前後で会社の方向性に変化はありましたか?
西川氏:大きく変わりましたね。お客さんの事業撤退や生産拠点の海外移転が相次ぎました。例えば、当時の私たちの事業の柱となっていたのは半導体基板の製造関連治具でした。「これは絶対になくならない。」と思っていたのに、次々と工場が海外に移転していったんです。
取引先が韓国、フィリピン、中国と工場を海外に展開していく中で、日本での生産拠点がなくなっていった。かといって当社には海外についていくほどの企業体力もない。残された日本国内の下請け会社同士で価格競争が始まり、1万円で売れていたものが、次第に8,000円、6,000円と下がっていく。
そこで気づいたんです。「ここに留まっていてはいけない。」と。価格競争をするしかない状況に身を置くのは避けたかった。食うのも嫌だし、食われるのも嫌だと。
その危機感が新しい分野への挑戦へとつながるのですね。
西川社長:そうです。全く新しい海に出ていくにしても、同じような競争が激しい分野では厳しい。そこで、ニッチな市場、特異性のあるところを探しました。
自社製品開発の歩み
自社製品に取り組まれてきた変遷を教えてください。
西川氏:最初は障がいのある方がボウリングを楽しむためのボウリング投球機を開発しました。車いすに装着して使います。床置き型の器具と異なり、投球機にもキャスターが付いているため「狙って投げる」「勢いよく押して投げる」といった楽しみ方ができます。
次にアーチェリー用具に取り組みました。中央のハンドル部分を当社の技術で作っています。ハンドルにリムと呼ばれるばねを装着して弓として使います。
同じくスポーツ分野では、その後カヌースラローム競技に使うゲート器具を開発しました。カヌースラローム競技でコース内に設置されるゲートです。国際カヌー連盟(ICF)より国際大会での使用認証を取得していて、この認証を得ているのは世界で2社だけです。
さらに、近年はカーボンフリー超小型モビリティに挑戦しています。特定小型原動機付自転車というカテゴリーが生まれたことで参入が可能になりました。

写真左:ボウリング投球機、写真右:アーチェリー リカーブハンドル(株式会社西川精機製作所提供)

写真左:カヌースラロームゲートシステム、写真右:カーボンフリー超小型モビリティ(株式会社西川精機製作所提供)
一見するとどれも全く異なる分野への挑戦ですね。
西川氏:よく言われます(笑)。車も作っているし、アーチェリーも作っているし、何だかわけわからない会社だと。でも実は、部品を作る機械や技術は同じです。だから、何をもって違うというのかわからなくて、私にとっては不思議なくらい。
どの製品も自社の強みの応用なのですね。
西川氏:そうですね。主軸となっている業界以外の仕事に取り組むと、「異業種の仕事を受けている」といった言い方をよくされます。でもそれは自社やエンドユーザーの業界までひっくるめた、特定の業種を仕事として頭に刷り込みすぎているのかなと思います。その垣根を持っていると、一生何もできなくなってしまう気がしますね。
新規事業の成功要因
新規事業の成功要因はどこにあるのでしょうか。
西川氏:やはり「0を1にする」ということです。私は最近よく言うんですが、「うちは0を1にする会社であり、最終的にはその1を10くらいまで伸ばしたい会社です。」と。
中小企業の多くは「1を10にする」、つまり既存の技術や製品を改良して大きくしていくことには長けていますが、「0」から何かを生み出すのが苦手です。お付き合いしている多くの中小企業の皆さんは、「1を10にする」ことに関してはめちゃくちゃ優れているんですよ。でも、掛け算の世界と同じで、「0」にいくら何をかけても「0」のまま。その発想の根幹となる「こうしたい」というコアがなければ何も始まらない。
アーチェリーハンドルはどのように生まれたのでしょうか。
西川氏:アーチェリーは、世界では競争が激しいものの、日本には弓を作るメーカーがほとんどなかった。かつては日本にも複数のメーカーがありましたが、2010年頃にはほとんど撤退していて、「日本の洋弓の製造技術はこのまま消えてしまう」という状況でした。「じゃあ、1つくらい作ってみようかな」と思って、見よう見まねで作ったのが最初です。それが「0を限りなく1にした」瞬間でした。
それをアーチェリーの指導者に見せたんです。すると色々と意見をもらえました。「これいいですね」っていう言葉より、「ここが駄目なんじゃない」っていうのは値千金の言葉ですね。
実物があると「本気なんだな」と分かってもらえて、「本気でやるんだったら、アーチェリーを実際に作れる人間を探すのを手伝うよ。」と言ってくれる人が出てきた。だから、その最初の一歩を踏み出すか踏み出さないかは全然違います。

純国産のアーチェリーハンドル SH-02(株式会社西川精機製作所提供)
業種 精密機械加工業
設立年月 1960年6月
資本金 1000万円
従業員数 8人
代表者 西川喜久
本社所在地 東京都江戸川区中央 1-16-23
電話番号 03-3674-3232
公式HP https://nishikawa-seiki.co.jp/