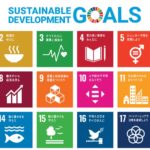- 2025-4-8
- 取材・インタビュー
新たな挑戦を結実へと導く出会い
第一回では、株式会社西川精機製作所の沿革と、自社製品開発への歩みを紹介しました。第二回では、新製品開発に至るまでのシーズや着想の発見と、具体的に開発を進めていく取り組みについてお話を伺いました。

株式会社西川精機製作所 代表取締役 西川喜久氏
「0から1」への挑戦でのハードルとその克服
「0を1にする」という思いはどのように養ってきたのでしょうか。
西川氏:私の場合、特に養ってきたわけではないんです。リーマン・ショックが来て、このままではジリ貧になるか、何とかして新しい何かに取り組むかという、究極の選択が見えてきました。ここからどう事業を切り返すかを考えるうちに、新しい事業を起こそうという気持ちが自然と生まれました。
リーマン・ショックの前までは、このまま人生も上がるしか無いなと思うぐらい勢いのある時期がありました。そのときは今の仕事をさらに追求して、会社を大きくするという感覚しかなかったです。そういうときには新たなものにチャレンジしよう、取り組んでいこうとは本当に考えていなかった。茹でガエル理論ですね。気づかないうちに危機に陥ってしまう。今は茹で上がる前に何とかして、鍋から出ようという努力を続けています。
新たな市場開拓の取捨選択
どのように新たな市場を発見しているのでしょうか。
西川氏:リーマン・ショック以降、何とかして生き残らなければという意識で、自分たちのノウハウや技術は何にリンク出来るのかを自問してきました。イベントを見に行ったり、シーズ発表会などで、先生方の話を聞いたりして、「この研究に使う機械だったら、うちで手伝えそうだな」とか考えて。そうしたリンクの仕方を頭の中で常に反芻しています。自社のノウハウや技術が厳然とあって、頭の中にしっかりと持っていれば、それを応用できる場所はあちこちで見つかります。
そうした機会に出て行って「リンク」を見つけるのですね。
西川氏:まさしく先日も中小企業を応援するという趣旨のイベントに参加して話してきました。そこでも、「なぜ色々なアイデアが湯水のように湧き出るんですか。」と聞かれましたが、アイデアなんて全然出ていないんですよ。「これ繋がれる。」というひらめきしかない。単純に、「そういう出会いを生む場所に自分で行っていますか?」という話だけだと思います。そういう人と出会い、ご紹介をもらっていますか、ということです。

アーチェリー リカーブハンドルの展示会出展(株式会社西川精機製作所提供)
社外との連携の重要性
社外との連携について、具体的にはどのように進めていますか?
西川氏:私が大切にしているのは、とにかく多くの人と出会い、話をすることです。過去5年で3,000〜3,500枚の名刺が溜まっていますが、実際に連携できるのはほんの一握りです。例えば展示会、セミナー、業界イベントなどには積極的に参加します。ダイレクトメールも送らせていただきます。皆さんに迷惑をかけているかもしれませんが(笑)。そんなものを見ても関係ないやと言って、情報をシャットダウンしてしまえば見なくて済むものも増えますが機会も失います。「ちょっとヒントになるかも」「面白そうだな」と思ったことには飛び込んでいきます。
その中から具体的な繋がりはどのように生まれるのですか?
西川氏:特に連携が進むのは、2〜3回何らかの形で会っている方や、間接的に情報をもらっている方との出会いからです。「あの人はこんなことをやっている」「この会社はこういう課題を持っている」という情報を得た上で、事前に自分の中で色々と想像してから実際に出会うと繋がる可能性が高まります。
あとは、東京都振興公社などのコーディネーターさんがお膳立てしてご縁を作ってくださる場合は、そのコーディネーターさんから見て、当社に必要なものや、先方の課題に当社の技術が繋がると分かった上での紹介なので、さらに早く繋がりができます。
超小型モビリティへの参入はどのようなきっかけだったのでしょうか?
西川氏:トヨタ紡織さんとの出会いが大きいですね。彼らは燃料電池の中核部品である「セパレーター」を製造しています。燃料電池バスなどで使われている、水素から発電する装置の部品です。彼らは規制が少ない低圧の水素ガスタンクを使うことで市場を広げられないかと実験的なトライアルを重ねていたところでした。そこで東京都振興公社で自動車関連が得意なコーディネーターさんが当社に繋いでくれました。
私たちは特定小型原動機付自転車の車両を開発したいと思っていました。ただ、市場にはシェアサービスの電動キックボードのような、先進的なものがすでにあって、同じものを作っても意味がない。それで私たちは四輪で丸ハンドルの車のような形を考えていました。しかし、それだけではただのゴーカートのような車になってしまう。何か特色を付けないといけないと悩んでいたところ、燃料電池という話が舞い込んできたんです。これを搭載することで走行距離も伸び、未来のある技術にチャレンジできる。そして世界に類を見ないものが作れるとイメージができてスイッチが入りましたね。それで今の形になっていきました。

カーボンフリー超小型モビリティ(株式会社西川精機製作所提供)
新たな挑戦に向けた社内文化醸成、意識改革
新たな挑戦に取り組むための社内文化はどのように形作られたのですか?
西川氏:挑戦は「やりたくない」という社員ばかりです(笑)。人間は誰でも基本的に今ある業務以外をしたくないものです。社員からは「また新しい業務が入ったら本業はどうするんですか」という声も出ます。でも、機運のタイミングって見えるじゃないですか。半年後にこの製品を持っていって営業したら大きな反響になるなって。それで「良いよね」と評価が得られて初めて、仕事として現実的な話が舞い込んでくる。
だから、「今このタイミングを逃すと、冬に種をまくようなもの。春に種をまかないと実らないよ。」と説得しています。
社員を説得する際のポイントは?
西川氏:先にスケジュールを組むことです。例えば補助金を活用すると、補助金は単年度勝負なので「補助金の期限内に成功させなければならない。」という制約が生まれます。我々もちょっとずるいけれど、そうした外部からの制約があると、社員も動かざるを得なくなります。 それで現物ができあがり、テレビに取り上げられたり、行政の人が「先駆的ですね」と褒めてくれたりすると、社員も悪い気はしないですね。実際に成果が出て、「これだけ評価されているよ」と伝えることで、次第にポジティブなサイクルが回り始めます。

純国産アーチェリー弓具メーカーへの進出で東京都経営革新優秀賞 奨励賞を受賞
業種 精密機械加工業
設立年月 1960年6月
資本金 1000万円
従業員数 8人
代表者 西川喜久
本社所在地 東京都江戸川区中央 1-16-23
電話番号 03-3674-3232
公式HP https://nishikawa-seiki.co.jp/






と-山田信一社長(写真右)-150x150.jpg)


-150x150.jpg)